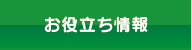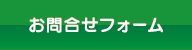2017年02月01日 [Default]
飲食店の店長は管理監督者かどうか?
答えは大方「NO」でしょう。
よって、残業手当や休日出勤手当等支払わなければなりません。
いわば一般従業員と変わらないのです。
しかし、多くの飲食店では「店長なのだから」という理由で「長時間労働」「残業代未払い」という待遇となっております。
非常に危険な状況であることを知っておいていただきたいと思います。
先日も大手飲食業のフランチャイズ店の店長が長時間労働が原因で過労死したことに対する裁判所の判決がありました。
結果は会社側の「安全配慮義務違反」を認めて、会社と社長に約4600万円の支払いを命じました。
この店長は、2店舗で店長を務め、過労死前直近6ヶ月の時間外労働の平均が月112時間を超えていました。
会社はそういった事実を知りながら「業務の軽減措置を取らなかった」と判決では指摘しました。
飲食店は店長ならずとも長時間労働になりがちな労働時間管理が難しい業界です。
残業を減らすためには多くのアルバイトを雇うなどしないと店が回りません。
しかしながら現状では、多くの飲食店は社員に残業のしわ寄せがいってしまっている状況でしょう。
そして、社員が足りない場合は当然店長に全てしわ寄せが来ます。
会社としては店長に時間管理も含めて店を任せているつもりだと思います。
従業員としても、「店長」という肩書が付けばモチベーションは当然上がるでしょう。
この関係が重要だと考えます。

やはり会社は店長、社員、アルバイトすべての勤務時間等は把握しておかなければなりません。
店長になった従業員は確実に売り上げを上げなければと今まで以上に頑張るでしょう。
この頑張りすぎを見逃すと不幸な事件につながってしまいます。
「店長頑張ってるな」だけではなく、「ちょっと頑張りすぎてないか?」という管理もしなければいけません。
「頑張ってくれてありがたいけど、しっかり休む時は休みなさい」というような声掛けだけでも変わるでしょう。
当事務所にも飲食店のお客様がいらっしゃいます。
やはり時間管理は非常に難しいのが実情です。
しかし、すぐに残業なしなんて考えずに、少しずつ、「1日30分ずつ減らしてみよう」というような努力はしていく必要がある時代です。
国としても重要政策として取り組み始めているので、この機会に長時間労働削減策を練っていくべきでしょう。
刑事告訴、過労死、長時間労働による疾病、損害賠償、慰謝料、未払い残業訴訟・・・
そんなことに自社が巻き込まれないようにしていくリスク管理が今ほど必要な時はありません!
経営者の皆様とともに取り組んでいきたいと切に思います。
答えは大方「NO」でしょう。
よって、残業手当や休日出勤手当等支払わなければなりません。
いわば一般従業員と変わらないのです。
しかし、多くの飲食店では「店長なのだから」という理由で「長時間労働」「残業代未払い」という待遇となっております。
非常に危険な状況であることを知っておいていただきたいと思います。
先日も大手飲食業のフランチャイズ店の店長が長時間労働が原因で過労死したことに対する裁判所の判決がありました。
結果は会社側の「安全配慮義務違反」を認めて、会社と社長に約4600万円の支払いを命じました。
この店長は、2店舗で店長を務め、過労死前直近6ヶ月の時間外労働の平均が月112時間を超えていました。
会社はそういった事実を知りながら「業務の軽減措置を取らなかった」と判決では指摘しました。
飲食店は店長ならずとも長時間労働になりがちな労働時間管理が難しい業界です。
残業を減らすためには多くのアルバイトを雇うなどしないと店が回りません。
しかしながら現状では、多くの飲食店は社員に残業のしわ寄せがいってしまっている状況でしょう。
そして、社員が足りない場合は当然店長に全てしわ寄せが来ます。
会社としては店長に時間管理も含めて店を任せているつもりだと思います。
従業員としても、「店長」という肩書が付けばモチベーションは当然上がるでしょう。
この関係が重要だと考えます。

やはり会社は店長、社員、アルバイトすべての勤務時間等は把握しておかなければなりません。
店長になった従業員は確実に売り上げを上げなければと今まで以上に頑張るでしょう。
この頑張りすぎを見逃すと不幸な事件につながってしまいます。
「店長頑張ってるな」だけではなく、「ちょっと頑張りすぎてないか?」という管理もしなければいけません。
「頑張ってくれてありがたいけど、しっかり休む時は休みなさい」というような声掛けだけでも変わるでしょう。
当事務所にも飲食店のお客様がいらっしゃいます。
やはり時間管理は非常に難しいのが実情です。
しかし、すぐに残業なしなんて考えずに、少しずつ、「1日30分ずつ減らしてみよう」というような努力はしていく必要がある時代です。
国としても重要政策として取り組み始めているので、この機会に長時間労働削減策を練っていくべきでしょう。
刑事告訴、過労死、長時間労働による疾病、損害賠償、慰謝料、未払い残業訴訟・・・
そんなことに自社が巻き込まれないようにしていくリスク管理が今ほど必要な時はありません!
経営者の皆様とともに取り組んでいきたいと切に思います。
2017年01月30日 [Default]
政府が長時間労働を制限する「働き方改革」の調整案を出しました。
内容は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(通称36協定)の改正と厳罰化です。
ご存知の方も多いと思いますが、労働基準法では「1日8時間」「1週40時間」と労働時間の上限を設けています。
この時間を超えて従業員を残業させる場合には、あらかじめ労働基準法36条に基づいて労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出ると、一定の残業が許されます。
「一定」の残業とは、月45時間、年間360時間以内というのが基準となっています。
しかし、年間において業務の繁閑がある企業はこの時間では足りません。
そういった観点から「特別条項」を付けると「一定」の残業時間を超えてもよいことになっております。
これが落とし穴とみられています。
例えば、繁閑など関係なく特別条項を付与して長時間労働をさせる。
特別条項に過労死ラインの100時間等の残業時間を設定して、実際にその時間もしくはそれ以上働かせる等々。

というわけで、下記のような案で調整する予定です。
〇 残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とする
〇 繁忙期は、最大で月100時間、2ヶ月平均80時間までの残業は認める
〇 罰則を科す
いかがでしょうか?
厳しい!!と思いますか?
正直申し上げて私は、「その程度か」というのが感想です。
私は、経営者の味方であり、労働者の味方でもあります。
まず経営者目線で見ると・・・。
<特別条項は今まで通り使えるし、だいたい60時間以内に抑えるようにし、最大でも80時間までは大丈夫だな>
<そんなに極端に厳しくなってないから良かった>
次に労働者目線で見ると・・・。
<この程度の改革案で何か変わるのかな・・・>
<結局「過労死ライン」に行かない程度に残業することになるのでは・・・>
あくまで私見ですので何とも言えませんが確かに難しい問題であることは間違いありません。
極端に残業規制してしまえば、中小企業などは経営が立ち行かなくなる可能性すらあります。
従業員にしてみても、今までもらえた残業手当が少なくなって生活が困る、なんて方も多いでしょう。
とにかく一番大事なのは「コストパフォーマンス」を上げることだと思います。
短時間で成果を上げることを追求していくことが残業削減につながるでしょう。
実際に残業を無くしたら売り上げや利益が上がったという会社をよく聞きます。
直ぐにとはいかなくても、これからの時代は「時間より成果」であることは間違いありません。
昔みたいに、残業していれば評価される時代はとっくに終わっています。(一部で残っていますが・・・)
経営者と労働者が知恵を出し合い、努力してウィンウィンの関係を築くのが一番です。
結果として、「売上・利益向上」「残業削減」「ワークライフバランス実現」「社員の定着」「健康」・・・
実現できれば最高です。
我々社会保険労務士も良いアイデアを出してサポートしていかなければいけないと強く思います。
内容は、「時間外労働・休日労働に関する協定届」(通称36協定)の改正と厳罰化です。
ご存知の方も多いと思いますが、労働基準法では「1日8時間」「1週40時間」と労働時間の上限を設けています。
この時間を超えて従業員を残業させる場合には、あらかじめ労働基準法36条に基づいて労使協定(36協定)を結び、労働基準監督署に届け出ると、一定の残業が許されます。
「一定」の残業とは、月45時間、年間360時間以内というのが基準となっています。
しかし、年間において業務の繁閑がある企業はこの時間では足りません。
そういった観点から「特別条項」を付けると「一定」の残業時間を超えてもよいことになっております。
これが落とし穴とみられています。
例えば、繁閑など関係なく特別条項を付与して長時間労働をさせる。
特別条項に過労死ラインの100時間等の残業時間を設定して、実際にその時間もしくはそれ以上働かせる等々。

というわけで、下記のような案で調整する予定です。
〇 残業時間の上限を繁忙期も含めて年間720時間、月平均60時間とする
〇 繁忙期は、最大で月100時間、2ヶ月平均80時間までの残業は認める
〇 罰則を科す
いかがでしょうか?
厳しい!!と思いますか?
正直申し上げて私は、「その程度か」というのが感想です。
私は、経営者の味方であり、労働者の味方でもあります。
まず経営者目線で見ると・・・。
<特別条項は今まで通り使えるし、だいたい60時間以内に抑えるようにし、最大でも80時間までは大丈夫だな>
<そんなに極端に厳しくなってないから良かった>
次に労働者目線で見ると・・・。
<この程度の改革案で何か変わるのかな・・・>
<結局「過労死ライン」に行かない程度に残業することになるのでは・・・>
あくまで私見ですので何とも言えませんが確かに難しい問題であることは間違いありません。
極端に残業規制してしまえば、中小企業などは経営が立ち行かなくなる可能性すらあります。
従業員にしてみても、今までもらえた残業手当が少なくなって生活が困る、なんて方も多いでしょう。
とにかく一番大事なのは「コストパフォーマンス」を上げることだと思います。
短時間で成果を上げることを追求していくことが残業削減につながるでしょう。
実際に残業を無くしたら売り上げや利益が上がったという会社をよく聞きます。
直ぐにとはいかなくても、これからの時代は「時間より成果」であることは間違いありません。
昔みたいに、残業していれば評価される時代はとっくに終わっています。(一部で残っていますが・・・)
経営者と労働者が知恵を出し合い、努力してウィンウィンの関係を築くのが一番です。
結果として、「売上・利益向上」「残業削減」「ワークライフバランス実現」「社員の定着」「健康」・・・
実現できれば最高です。
我々社会保険労務士も良いアイデアを出してサポートしていかなければいけないと強く思います。
2017年01月23日 [Default]
連合の調査結果で、採用面接の際に残業や休日出勤ができるか聞いている企業が36.6%あったとの結果が出ました。
ちなみに転勤できるか聞いている企業は43.9%あったそうです。
何故このような調査をしているかというと、「大半の企業は男女を問わず質問しているが、結果的に残業しにくい人が多い女性を採用しないことにつながらないか」と心配しているようです。

う〜ん、私はそんなこと言ってたら求める人材を採用することができなくなる・・・と思うのですが。
残業できるかできないか?休日出勤できるかできないか?大切ですよね!!
後で問題にならないためにも、あらかじめ確認することは企業にとっては重要だと思います。
残業の質問をしないで、採用した人に「こんなに残業あるなんて聞いていない」なんて言われたら困りますよね。
一昔前までは当たり前のことが、問題視されているとつくづく思います。
「転勤はできますか?」
私も過去に面接で自分が聞かれたことがあります。
「できません」
私ははっきり返答させていただきました(笑)
部屋を出た後で、「もったいないな〜、転勤できればな〜」という面接官の声が聞こえたのを覚えています。
残業も同じことですよね。
聞かれたらはっきり答えればいいじゃないですか。
どのくらいあるのかが不安なら「月に何時間くらいありますか?」と聞いていいと思います。
面接の時点で信頼関係を築いておけば、採用後も変な問題は起きにくいと思います。
ちなみに「してはいけない質問」をしている企業も結構あるようです。
ここはしっかり学んで気をつけなければいけません。
例えば
〇本籍に関する質問
〇住居やその環境についての質問
〇家族構成や家族の職業、地位、収入に関する質問
〇資産に関する質問
〇思想・信条、宗教、尊敬する人物、支持政党に関する質問
〇男女雇用機会均等法に抵触する質問
漠然と並べましたが、細かく見ると結構知らないうちに質問していることがあるかもしれません。
この機会に確認いただければと思います。
今は売り手市場でただでさえ採用担当者は難しい状況だと思います。
私のお客様もかなり困っていらっしゃいます。
ただ、妥協して採用しても長続きはしません。
こんな時だからこそ、選考に来た方を見極め、会社の財産となる「人財」を発掘できるよう頑張りましょう!
ちなみに転勤できるか聞いている企業は43.9%あったそうです。
何故このような調査をしているかというと、「大半の企業は男女を問わず質問しているが、結果的に残業しにくい人が多い女性を採用しないことにつながらないか」と心配しているようです。

う〜ん、私はそんなこと言ってたら求める人材を採用することができなくなる・・・と思うのですが。
残業できるかできないか?休日出勤できるかできないか?大切ですよね!!
後で問題にならないためにも、あらかじめ確認することは企業にとっては重要だと思います。
残業の質問をしないで、採用した人に「こんなに残業あるなんて聞いていない」なんて言われたら困りますよね。
一昔前までは当たり前のことが、問題視されているとつくづく思います。
「転勤はできますか?」
私も過去に面接で自分が聞かれたことがあります。
「できません」
私ははっきり返答させていただきました(笑)
部屋を出た後で、「もったいないな〜、転勤できればな〜」という面接官の声が聞こえたのを覚えています。
残業も同じことですよね。
聞かれたらはっきり答えればいいじゃないですか。
どのくらいあるのかが不安なら「月に何時間くらいありますか?」と聞いていいと思います。
面接の時点で信頼関係を築いておけば、採用後も変な問題は起きにくいと思います。
ちなみに「してはいけない質問」をしている企業も結構あるようです。
ここはしっかり学んで気をつけなければいけません。
例えば
〇本籍に関する質問
〇住居やその環境についての質問
〇家族構成や家族の職業、地位、収入に関する質問
〇資産に関する質問
〇思想・信条、宗教、尊敬する人物、支持政党に関する質問
〇男女雇用機会均等法に抵触する質問
漠然と並べましたが、細かく見ると結構知らないうちに質問していることがあるかもしれません。
この機会に確認いただければと思います。
今は売り手市場でただでさえ採用担当者は難しい状況だと思います。
私のお客様もかなり困っていらっしゃいます。
ただ、妥協して採用しても長続きはしません。
こんな時だからこそ、選考に来た方を見極め、会社の財産となる「人財」を発掘できるよう頑張りましょう!