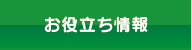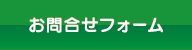2016年05月02日 [Default]
通常、自社の従業員を「海外派遣」する場合は、労災保険の特別加入の手続きを行わなければなりません。
この手続きを怠っていると、海外派遣した従業員が派遣先で労災に遭ったときに給付が受けられない可能性があります。
海外派遣の特別加入者の範囲は以下のいずれかに該当する人です。
①日本国内から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
※日本国内の事業主とは、日本国内で労災保険の保険関係が成立している事業(有期事業を除く)の事業主
※海外で行われる事業とは、海外支店、工場、現地法人、海外の提携先企業など
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模(日本の中小企業に当たる規模)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
③独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
上記のような従業員を海外派遣させる場合は、所定の用紙記載の上、労働基準監督署(労働局)にて手続きが必要です。
先日、運送会社の社員として海外の現地法人に赴任中に過労死した男性に対し日本の労災保険が適用されるか争われた訴訟の判決がありました。
この男性の会社は海外派遣の特別加入をしておらず、一審では労災適用を認めない判決を言い渡していました。
しかし、今回は「日本からの指揮命令関係などの勤務実態を踏まえて判断するべきだ」「男性は本社の指揮命令下で勤務していた」として、労災保険の適用が認められました。
ちなみに過労死1ヶ月前の時間外労働は約104時間だったとのことです。
多くの企業が、この「海外派遣の特別加入」を行っておらず、海外赴任者の労災が認められなかったケースが多かったと思われます。
その意味では画期的な判決ですが、やはり制度として「海外派遣の特別加入」があるのですから、従業員を海外に派遣する場合は事前に手続きを行うべきでしょう。
ちなみによくある相談で「海外派遣」と「海外出張」の区別があります。
「海外派遣」は先にも述べた要件を満たす人で労災保険による「海外派遣の特別加入」による「給付が受けられます。
「海外出張」は例えば、商談、打ち合わせ、会議、調査、視察、見学、突発的なトラブル対処などで短期的に海外に行くケースです。
「海外出張」中の労災については、通常のその方が所属する事業場の労災により給付を受けられます。
上記ご理解の上、適切な手続きを行ってください。

この手続きを怠っていると、海外派遣した従業員が派遣先で労災に遭ったときに給付が受けられない可能性があります。
海外派遣の特別加入者の範囲は以下のいずれかに該当する人です。
①日本国内から、海外で行われる事業に労働者として派遣される人
※日本国内の事業主とは、日本国内で労災保険の保険関係が成立している事業(有期事業を除く)の事業主
※海外で行われる事業とは、海外支店、工場、現地法人、海外の提携先企業など
②日本国内の事業主から、海外にある中小規模(日本の中小企業に当たる規模)に事業主等(労働者ではない立場)として派遣される人
③独立行政法人国際協力機構など開発途上地域に対する技術協力の実施の事業(有期事業を除く)を行う団体から派遣されて、開発途上地域で行われている事業に従事する人
上記のような従業員を海外派遣させる場合は、所定の用紙記載の上、労働基準監督署(労働局)にて手続きが必要です。
先日、運送会社の社員として海外の現地法人に赴任中に過労死した男性に対し日本の労災保険が適用されるか争われた訴訟の判決がありました。
この男性の会社は海外派遣の特別加入をしておらず、一審では労災適用を認めない判決を言い渡していました。
しかし、今回は「日本からの指揮命令関係などの勤務実態を踏まえて判断するべきだ」「男性は本社の指揮命令下で勤務していた」として、労災保険の適用が認められました。
ちなみに過労死1ヶ月前の時間外労働は約104時間だったとのことです。
多くの企業が、この「海外派遣の特別加入」を行っておらず、海外赴任者の労災が認められなかったケースが多かったと思われます。
その意味では画期的な判決ですが、やはり制度として「海外派遣の特別加入」があるのですから、従業員を海外に派遣する場合は事前に手続きを行うべきでしょう。
ちなみによくある相談で「海外派遣」と「海外出張」の区別があります。
「海外派遣」は先にも述べた要件を満たす人で労災保険による「海外派遣の特別加入」による「給付が受けられます。
「海外出張」は例えば、商談、打ち合わせ、会議、調査、視察、見学、突発的なトラブル対処などで短期的に海外に行くケースです。
「海外出張」中の労災については、通常のその方が所属する事業場の労災により給付を受けられます。
上記ご理解の上、適切な手続きを行ってください。

2016年05月02日 [Default]
5月1日に茅ヶ崎市の海岸で開かれた湘南祭に行ってきました。
この湘南祭は4月30日から2日間行われました。
毎年行っておりますが、いつもすごい人出です。
会場には出店が立ち並び、ステージではいろいろな歌や踊り、浜辺では催し物と盛りだくさんです。
こんな感じです。

屋台がたくさん出て、みなさんビール片手に楽しそうです。

ステージでは歌やイベント盛りだくさんです。

何人来ていたのでしょうか?
非常に楽しい1日でした。
私、社会保険労務士目線で会場を歩いていると、いろいろ考える1日でもありました。
地元の茅ヶ崎市のお役に立つため、商工会議所など各種団体に加入して協力していきたい。
中小企業のブースも何店かでており、皆さん協力して頑張っている。
パンフレットに掲載されている協賛企業には様々なな各種団体、企業名があり、社会保険労務士事務所も載っていた。
当事務所もまだまだ茅ヶ崎市、いや神奈川県のためにできることは沢山あります。
今後は、仕事ばかりではなくこういったことにも力を入れていきたいと思いました。
ちなみに茅ヶ崎市は、最近ひそかに祭りの多い町として知られています。
ついこの間は大岡越前祭がありました。
5月中にはまた、海岸近くでアロハマーケットという催しがあります。
その他にも、年中祭りが開かれています・・・(笑)
楽しい街です!!

最後は茅ヶ崎の象徴である烏帽子岩を見ながらのんびりと過ごし帰宅しました。
私は本当に茅ヶ崎市が大好きです。
これからも茅ヶ崎市の発展に貢献できればと強く思っております。
この湘南祭は4月30日から2日間行われました。
毎年行っておりますが、いつもすごい人出です。
会場には出店が立ち並び、ステージではいろいろな歌や踊り、浜辺では催し物と盛りだくさんです。
こんな感じです。

屋台がたくさん出て、みなさんビール片手に楽しそうです。

ステージでは歌やイベント盛りだくさんです。

何人来ていたのでしょうか?
非常に楽しい1日でした。
私、社会保険労務士目線で会場を歩いていると、いろいろ考える1日でもありました。
地元の茅ヶ崎市のお役に立つため、商工会議所など各種団体に加入して協力していきたい。
中小企業のブースも何店かでており、皆さん協力して頑張っている。
パンフレットに掲載されている協賛企業には様々なな各種団体、企業名があり、社会保険労務士事務所も載っていた。
当事務所もまだまだ茅ヶ崎市、いや神奈川県のためにできることは沢山あります。
今後は、仕事ばかりではなくこういったことにも力を入れていきたいと思いました。
ちなみに茅ヶ崎市は、最近ひそかに祭りの多い町として知られています。
ついこの間は大岡越前祭がありました。
5月中にはまた、海岸近くでアロハマーケットという催しがあります。
その他にも、年中祭りが開かれています・・・(笑)
楽しい街です!!

最後は茅ヶ崎の象徴である烏帽子岩を見ながらのんびりと過ごし帰宅しました。
私は本当に茅ヶ崎市が大好きです。
これからも茅ヶ崎市の発展に貢献できればと強く思っております。
2016年04月28日 [Default]
経営者、部下がいる方は特に、従業員の日々の様子を見ておくことが求められます。
何が言いたいか、というと下記のようなことがあるからです。
某社の男性従業員が自殺したのは、「うつ症状があったのに会社が適切な対処をしなかったためだ」として、遺族が同社に損害賠償を求めた裁判の判決があり、裁判所は遺族の訴えを認め損害賠償支払い命令が出されました。
男性社員は営業を主に行っていたが、ある時から不眠などの症状で通院を始め、その後自殺に至ったとのことです。
自殺前の男性社員は、「ミスが急増した」、「自分は仕事が遅いと発言していた」などの様子が判明していたとのことです。
そのうえで判決では、「上司は自殺前に男性社員がうつ病などを発症していたことを認識できた」、「男性社員の仕事を軽くするなど、緊急対応をしていれば自殺は防げた可能性が高い」と判断しました。
会社には従業員を管理する義務が課せられています。「善管注意義務」というものです。
「分からなかった」「気づかなかった」では済まされないことがよくわかると思います。
このようなことが起これば、会社名も報道され、会社の信用は失墜し経営にも大打撃になるとともに、多額の賠償金や慰謝料の支払いもあります。
どうすればいいのか?
1・導入されたばかりの「ストレスチェック制度」を利用する
2・従業員相談窓口を設ける
3・定期的に部署ごとで仕事以外のことも含めたミーティングを実施する
4・経営者、上長含め社員全員がコミュニケーションを密にする
他にもいろいろあると思いますが、こうしたことをしっかり行っていれば、「会社が適切な対処を怠っていた」ということは防げる可能性は高いと思われます。
一番大切なのは、社内環境、職場環境をよくすることだと思います。
一人で悩むような環境を作らない。何かあったらすぐに気軽に相談できる仲間が身近にいるだけで全然変わってきます。
経営者の皆様は、会社の売り上げや利益だけでなく、こうした「ヒト」の管理も大切な仕事です。
「ヒト」に関する専門家は私ども社会保険労務士です。
やはり何事においても「リスク管理」が大切です。
お悩みがあれば、いや、悩む前にお気軽にご相談いただければと思います。

何が言いたいか、というと下記のようなことがあるからです。
某社の男性従業員が自殺したのは、「うつ症状があったのに会社が適切な対処をしなかったためだ」として、遺族が同社に損害賠償を求めた裁判の判決があり、裁判所は遺族の訴えを認め損害賠償支払い命令が出されました。
男性社員は営業を主に行っていたが、ある時から不眠などの症状で通院を始め、その後自殺に至ったとのことです。
自殺前の男性社員は、「ミスが急増した」、「自分は仕事が遅いと発言していた」などの様子が判明していたとのことです。
そのうえで判決では、「上司は自殺前に男性社員がうつ病などを発症していたことを認識できた」、「男性社員の仕事を軽くするなど、緊急対応をしていれば自殺は防げた可能性が高い」と判断しました。
会社には従業員を管理する義務が課せられています。「善管注意義務」というものです。
「分からなかった」「気づかなかった」では済まされないことがよくわかると思います。
このようなことが起これば、会社名も報道され、会社の信用は失墜し経営にも大打撃になるとともに、多額の賠償金や慰謝料の支払いもあります。
どうすればいいのか?
1・導入されたばかりの「ストレスチェック制度」を利用する
2・従業員相談窓口を設ける
3・定期的に部署ごとで仕事以外のことも含めたミーティングを実施する
4・経営者、上長含め社員全員がコミュニケーションを密にする
他にもいろいろあると思いますが、こうしたことをしっかり行っていれば、「会社が適切な対処を怠っていた」ということは防げる可能性は高いと思われます。
一番大切なのは、社内環境、職場環境をよくすることだと思います。
一人で悩むような環境を作らない。何かあったらすぐに気軽に相談できる仲間が身近にいるだけで全然変わってきます。
経営者の皆様は、会社の売り上げや利益だけでなく、こうした「ヒト」の管理も大切な仕事です。
「ヒト」に関する専門家は私ども社会保険労務士です。
やはり何事においても「リスク管理」が大切です。
お悩みがあれば、いや、悩む前にお気軽にご相談いただければと思います。